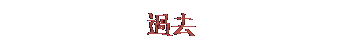
今から十年前、俺はある実業家の珠代という女性と結婚した。お互い好きで周りの反対を押し切っての結婚だった。
今思えば二人ともまだ幼くて、ままごとみたいな結婚だったが、二人の生活は楽しかった。
結婚とほぼ同時に子供にも恵まれた。倫子という女の子だ。
倫子は二人の希望だったが、二人の貯金が生活費でどんどん減っていくに連れて、俺たちは喧嘩が絶えなくなった。
お嬢様育ちでお金に苦労したことのなかった珠代と、貧しい家に育った俺とでは、生活やお金に対する考え方が合わず、恥ずかしながら子供の前で罵り合うこともしばしばだった。
あれは、忘れもしない6月、倫子は5歳だった。三人で外出していたあの日、俺と珠代は人目もはばからず外で口論になった。
珠代も俺も罵り合うことに夢中で、ちょっと目を離した隙に、そばを離れた倫子は、一人で横断歩道を渡ろうとして、脇見運転の車に...一瞬の出来事だった。
子供を失って、珠代との関係も程なくしてダメになった。珠代は実家に戻り、俺は家族を失った。一人ぼっちになった。
俺は言葉が続かなくなった。あの時の痛み、悲しさが蘇ってきて、ハートが張り裂けそうになった。
俺はこみ上げてくる感情を堪えるのに必死だった。
礼子は、俺が話す間、ずっと目線を合わせ続けた。
相づちを打ったりうなずいたりしながら俺の話を聞いていたが、俺がこみ上げてくる感情と必死に格闘しているのに呼応してか、目に涙が浮かんだかと思うと、それはつーっと頬を伝って流れた。
それを見た瞬間、俺は耐えられなくなって、横を向いて手で涙をこっそりと拭った。
「...それから俺は悲しさ寂しさを忘れるためがむしゃらに働いて、そして何とか食べていくのには困らないところまで来た。三人の生活のことを忘れていたわけではないが、あの時のことをゆっくり思い出すことはなかった。」
声が裏返ったりしないかとひやひやしたが、涙を拭ったことで少し落ち着いてきた俺は、続けた。
「大家の子供を遊園地に連れて行った日、帰りの電車で娘の倫子のことをすっと忘れていたことを思い出した。珠代とのことも...たぶんそれからだと思う、例の悪夢を見るようになったのは。」



